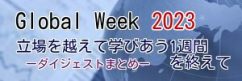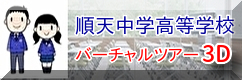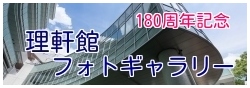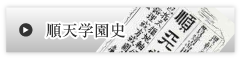お知らせ

お知らせ
グローバルウィーク・ダイジェスト2022 1日目(11/14実施分)
2016年に、SGHの活動の一環として始まり、「立場を超えて互いに学びあう1週間」をスローガンに、それ以来毎年実施しているGlobal Week。今年度は以前通り11月14日(月)~11月18日(金)の1週間を通して実施しました。
今回は11月14日(月)に行われた1日目のダイジェストを各トピックの運営担当者よりご報告致します。
◆トピックコード 101
「仕事とクリエイティビティⅡ」
hair stylist @hiji_hair マキノナツホ 先生
SPACE SHOWER MUSIC/Artist Director & Manage 菅友和 先生
インテリアデザイナー依木想太 先生
参加生徒数 生徒28名 報告者名 阿部邦宏
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
職業としての「研究者」というテーマで、研究者になるまでの道のりや、仕事内容についてご講演いただいた。生徒とのディスカッション形式をとった。研究者になるためには、大学院に進学したのちに、博士号を取ることが必要である。研究者の職場は、大学や研究所、製薬会社などの企業、博物館など多様であり、職場によっては、研究する内容が決まっていることもある。研究者にとって重要な要素としては、研究上のオリジナリティーである。就職できるまでの道のりが長く、お金もかかるので、周囲の理解が必要である、という現実的な話や、泉先生の職場での仕事内容など、具体的に研究者に関してお話いただき、生徒らも納得した様子であった。
2.生徒の感想
・今から、あれもこれもやらなければ、やってみてダメだ、才能ない、諦めようではなく、焦らずに、まず目の前のことをやる。歌いたいのであれば、じゃあ曲も作らなきゃ、あぁだめだ、となる前に、歌の練習を最優先にしてすごそうと負担が減った。
・自分の夢はまだ諦めなくてもいいということ。
・まだ可能性はあるからすぐに妥協せず、ギリギリまで粘ってみてもいいということ。
・自分が今まで全然知らなかった、専門的な分野について知れたこと。
・また、そのある職業に就くまでには、人それぞれ色々な道があるから、現時点で自分の向き不向きを考えなくてもいいと知れたこと。
◆トピックコード 102
「世紀の原爆写真は語る ―核兵器も戦争もない世界を―」
小学校教諭 学級担任 大西 知子 先生
参加生徒数 生徒20名 報告者名 栗原篤志
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
1945年(昭和20年) 8月6日 午前8時15分、広島に、人類史上初めて、原子爆弾が投下された。続く、8月9日 11時2分には、長崎に原子爆弾が投下され、ふたつの原子爆弾によって、21万人以上の方が亡くなり、15万人以上の方が負傷した。
DVD視聴 「きのこ雲の下で何が起きていたのか…」
⇒当時、写真撮影は禁止されていたが、一人の記者が、「伝えなければ…」という
自らの意志で撮影。原爆投下後、2キロ圏内は壊滅状態であった。
●私の目指す進路と「平和」をテーマに、今後何ができるのかを考える。
①今後の取り組みについて(活動内容・方法)
②活動の成果・発信方法
2.生徒の感想
・原爆が投下された日、どのようなことが起こっていたのか、残っている写真や、被爆者の方から話を聞いてみても、わからないことがまだまだ多く、被爆者の方も少なくなってきているので、今後二度とこのようなことが起きないように、原爆について知って、様々な人にも、知ってもらう必要があると思いました。平和にするにはどうしたらよいか、考えるきっかけになってよかったです。
・原爆によって被爆した人のことや、原爆症、被災状況などは、学校の授業や資料館などで知っていたが、原爆孤児や戦争孤児についてのことは、ほとんど知らなかったし、そこに焦点を当てて調べることもなかったので、自分にとってほぼ初めての内容だった。改めて、戦争の悲惨さや残酷さを考えさせられた。
◆トピックコード 103
「国際経営論について」
中央大学 国際経営学部 教授 咲川孝 先生
参加生徒数 17 名 報告者名 高谷哲司
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
多国籍企業とは、どのような企業かに始まり、多国籍企業の、成長とともに加速するグローバル化の現状と、それに反発する、脱グローバル化の動きなどについて、理解を深めた。ハーゲンダッツや、キットカットの抹茶味のように、多国籍企業による現地適合や、マクドナルドのように、同じ商品を世界中で販売するビジネスモデルなど、一口に多国籍企業と言っても、そのビジネス戦略は様々である点が紹介された。
また、生徒が事前に調べてきた多国籍企業について、話題提供者から、より詳細なエピソードなども提供され、テーマに対する生徒の興味関心を高めていた。
2.生徒の感想
・今回は、多国籍企業についてのお話でした。今まで聞いたことのない話を聞けて、役に立ったと思いました。また、実際の日本の企業で、具体的にお話をしてくださり、わかりやすかったです。
◆トピックコード 104
「地球環境と国際協力(仮)」
日本大学 国際関係学部 教授 鈴木和信 先生
参加生徒数 2 名 報告者名 川本真一
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
日本国内で、様々な課題が山積する中で、なぜ、地球環境の保全を行うことが必要なのか。この問いに、身近な製品や商品を例示しながら、それらが、地球のいろいろな場所、人との関わりを通して、手元に届いていることを、認識するところからスタートした。環境問題を、人と社会の「つながり」として捉え、たとえ、一人ができることは小さなことでも、つながりの中にいる一人、として振る舞うことが、環境保全に向けての第一歩であることを、いくつかの例を通して参加した生徒に問い、共に考えていく時間であった。
2.生徒の感想
・「発展途上国に対して、ただ与えるだけではなく、扱い方を教える必要があるということ。」に気づけた。
・「地球環境の問題とその現状」を、具体的な事例を通して知ることができた。
・「発展途上国での人々の生活」について、現地に直接足を運ばれたときの、人々とのやり取りも交えて、話してくださり、リアリティを感じることができた。
◆トピックコード 105
「地球接近天体の最新情報について」
日本科学技術ジャーナリスト会議 理事 山本威一郎 先生
参加生徒数 11名 報告者名 堀内進
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
地球が太陽系で誕生して、46億年が経過し、8惑星が太陽の周りを回っている。その中でも、火星と木星の軌道の間には、約100万個近い小天体があり、小惑星帯と呼ばれている。その中には、地球近くを通過する小惑星も、約3万個あり、いずれは地球に衝突すると、予想されている。約 6600 万年前に、地球に衝突した小惑星は、半径が10kmであると言われ、その影響で恐竜が絶滅したといわれている。
●1850年気仙沼隕石
●2012年45mの小惑星がニアミス
●2013年チェラビンスク隕石
などなど、毎日のように小惑星が飛来してくる。100mの惑星衝突で、国家的破壊が起き、1kmの惑星衝突で世界的破壊、10kmの惑星衝突で生命が絶命する。小さい惑星や太陽方向から飛来する惑星は観測しづらい。世界的なネットワークを構築して観測にあたり、衝突の回避をしなければならない。しかし、国家の予算がつかなくて困っている。
◎生徒たちは真剣に聴き、終了後に、何人かの生徒が質問をしていました。
2.生徒の感想
・何年後に衝突してくるかわからない小惑星を、今はスーパーコンピューターなどを使って、進路を予想し、ロケットをぶつからせて軌道を変えられることを、初めて知りました。
・世界は、目の前の戦争などに兵器を使い、人と人との争いが耐えないが、本当はこの先人類を絶滅させてしまうかもしれない、隕石の墜落を防ぐために兵器を使わなければならないと仰っていて、」本当にそのとおりだなと思いました。自分の国が生き残るため、勝つための戦争は幸せをもたらさないし、戦争に夢中で、隕石の墜落を防げず、人類が絶滅してしまったら、本末転倒だなと考えました。
◆トピックコード 106
「地球温暖化と気候変動について広い時空間スケールから考えてみよう」
千葉大学 准教授 泉 賢太郎 先生
参加生徒数10名 報告者名 神林絹枝
 |
 |
|---|
1.トピック内容等
人類が直面する、最大規模の環境問題を、大きなスケールで考えることの重要性。将来のリスク評価は、必ず不確定性を伴う。それでも、人類や国、個人は、その不確定性を伴う、限られた情報をもとに、将来に向けた行動を。選択しなければならない。さまざまな不確定性を考えたときに、どのように気候変動をするのかを、データで示した。
また、現在かつてない速さで温暖化しており、すでに気候変動の影響が現れている。気候システムは複雑で、よくわかっていないことも多い。しかし、世界中の科学者が、この不確かを減らそうとしている、とのことである。この不確実な要因については、普段考えたことがなかったため、自分で思っていたものとは、大きく異なる変化も、起こりうることを知った。大変興味深かった。
2.生徒の感想
・これから、どのくらい地球の温度が上昇するか、などの将来予測や、様々なパターンなど、自分だけではわからなかったことを、知ることができました。これから自分にできる対策を考え、実行したいです。
◆トピックコード 107
「UNHCRの難民支援と私たちにできること」
特定非営利活動法人国連UNHCR協会 天沼 耕平 先生
参加生徒数 10名 報告者名 小見山太郎
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
前半は、難民問題に関する、出張授業をおこなう学生団体「SOAR」に所属する、大学生2名による、ワークショップを実施しました。「いのちの持ち物けんさ」と題して、自分にとって、替わりのあるものは何か、替わりのないものは何か、について考え、家や仕事、身分を証明するもの、家族、心身の健康など、あらゆるものを失ってしまっているのが、「難民」であるということを学びました。後半は、国連UNHCRの天沼さんの講演です。日本人に、「難民」やUNHCRのミッションについて知っていただき、日本各地で難民支援のための寄付を集め世界各地に届ける活動をしています。「難民」とは、何を指す言葉なのか。「難民」と「移民」の違い。「難民」と「避難民」は違うのか。「難民」という言葉の定義の難しさ、あいまいさなどについて学び、生徒にとって、理解が深まる時間となりました。また、「難民に関するグローバルコンパクト」という言葉も学び、これからの難民問題への世界的な取り組みについても知ることができました。
2.生徒の感想
・”日本では、「ネット難民」や「結婚難民」など、「難民」という言葉が安易に使われているために、本来の「難民」という言葉が持つ深刻さが薄れている、という話がとても印象的でした。
・「難民」と「避難民」の違いについて知りました。普段意識することなく、聞き流していたと思います。ニュースを見る時に、注意してみたいと思います。
◆トピックコード 108
「新型コロナウイルスの抗原検査キットの原理を理解し、検査データの信頼性を統計学的に考察してみよう!」
日本薬科大学 准教授 齋藤 博 先生
参加生徒数 19名 報告者名 奥沢怜央
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
新型コロナウイルスで、一躍世に知られた「抗原検査」と「抗体検査」、「PCR検査」の違いの講義・説明から始め、齋藤先生がお持ちになった西洋わさび(ホースラディッシュ)を用いた、抗原検査の実験を行った。実験では、マイクロピペットなど、実験器具の使い方も指導された。また、コロナの全国新規感染人数や抗原検査の正確性のデータ計算を実際に行い、コロナ罹患率の割合や、抗原検査の信頼性なども講義した。
ウィズコロナの時代に入りつつある中、やみくもに抗原検査をすることは、医療従事者への負担増、データの信頼性の低下につながることも、講義の最後にお話しいただいた。
2.生徒の感想
・(生徒A)コロナが身近になり、抗原検査なども実際に行っているので、とても興味深く受講できた。
・(生徒B)医療従事者が実際に行う検査を行い、大変さがわかった。
◆トピックコード 109
「データサイエンスを体験してみよう ~野球のデータを用いて~」
横浜市立大学 大学院データサイエンス研究科 M2年 石井 伴直 先生
参加生徒数 10名 報告者名 白井恵美
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
データサイエンスについての概説があり、統計解析操作を実際に行った。
簡単な四則計算→統計計算→データを使った操作→ビッグデータを扱うと、段階的にRを用いて計算や可視化を行った。Google Chrome 上 で 動 く ツ ー ル、(Colaboratory)を用いて、簡単なデータ分析の演習が経験できる。
2.生徒の感想
・Excelを知った時よりも、大きな感動を得た。普段見ているデータは、このようにしてまとめられているんだと思った。
・エクセルでは扱いにくいデータも、colabratoryの使い方を学び、エクセルよりも簡単に扱うことが出来るようになった。新しい世界を知ることができた。
・データサイエンスの有効性がとても理解できた。
◆トピックコード 110
「Diversity matters. 学びの場に おける多様性の重要性について」
立命館アジア太平洋大学(APU) 東京オフィス 所長 伊藤 健志 先生
参加生徒数 6名 報告者名 デグラ・シェバ
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
この講義の主な目標は、多種多様なエスニシティ(国籍や文化圏)の中で学ぶ最大のギフトは、自分の無知や固定概念に気付くこと、一方的な物の見方から多角的なものの見方への転換である。アフガニスタンからのゲストスピーカーが来て、国や歴史、現在の状況について話してくれた。アフガニスタンのことは、マスコミのニュースで聞いているが、普段はあまり聞くことのない、アフガニスタンの情報を話してくれて、生徒たちは、リアルに知ることや、現地の方の声・体験を聞くことが出来た。また、中村 哲さんという、日本人のボランティア医師が、アフガニスタンに多大な貢献をし、人々から尊敬を集めているという話をした。最後のメッセージでは、「人間はそれぞれ違うけれど、みんな同じ」という価値観を強調された。ただ、ライフスタイルが違うだけなのである。だから、多様性の中に結束があるべきだということである。
2.生徒の感想
・今後にわたって、聞くことがもうないような、貴重な内容の話を、アフガニスタンの方本人から聞けて良かった。今回学んだように、世の中にはいろいろな考えを持っている人がいるので、たくさんの人と交流したい。
・いろんな知識をもって、いろんな見方をしてみることが、大切たと分かった。知識を広げるために、いろんな人と対話することが大事です。
・多様性を、もっと大切にしようと言うことは簡単だけど、実際に、状況などと合わせて考えてみると、国同士だったり、民族だったりと、対立してしまう部分がたくさんある、と気づきました。
◆トピックコード 111
「宇宙へ行くと人の心と体はどうなるの?~医学研究者、宇宙飛行士、宇宙旅行者の視点から考えてみよう~」
日本大学医学部 准教授 小川洋二郎 先生
参加生徒数 32名 報告者名 平田嘉納子
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
導入として、宇宙のキーワードとしてあげられるもの?スターウォーズや、宇宙戦艦ヤマト、スペースシャトル、スペースマウンテン。イメージとしてあげられるもの?暗闇、黒、青、果てしない、未知にあふれている、などがあげられていました。そこから国際宇宙ステーションの説明や、宇宙飛行士が帰還した直後に、体(むくみ、立てない、歩けない、脳貧血など)や心(閉鎖環境下での心の問題)が、どのように変化するのかを、写真や動画により詳しく説明がありました。後半で、長期滞在適性検査(白のジグソーパズル)の体験や、宇宙食の試食などもあり、興味関心がより高まったと思います。講師の先生も「宇宙飛行士や、宇宙に関することにかかわる人が、この中から出てくると嬉しいです」と、締めくくっていらっしゃいました。
2.生徒の感想
・宇宙に行くと、人の体に負担がかかるだけでなく、心にも大きな負担やストレスを受けるなか、任務を遂行していることがわかったこと。宇宙から帰ってきた時に、倒れてしまう理由を知れて良かった。体液が宇宙で減るというのは驚いた。
・宇宙と医学には、深い関わりがあったことが分かりました。人間の体は、様々な環境に順応できるのだと知りました。
◆トピックコード 112
「ニュースキャスターの仕事について 【卒業生企画】」
NHK BSニュース 「BSニュースWorld+Biz」キャスター 西岡愛 先生
参加生徒数 14名 報告者名 金子哲也
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
ハードウェアの進歩、ソフトウェアの進歩、私たちの生活の変化に関する解説をしたうえで、グループディスカッションをさせ、生徒に発言させ、その質問に講演者が答える、という形式のプログラムでした。生徒達の中には、自ら発言をする生徒も数名いたが、担当教員も生徒を指名するなどして、活性化に尽力した。最後の質疑応答でも、「IT業界で今後必要とされる人材は?」「IT人材に数学は必要か?」などの質問も出た。
2.生徒の感想
・キャスターの仕事内容がよく分かった。
・放送業界で、もう9年目となる西岡さんでも、新しい職場での最初の放送は、手が震えてしまうほど緊張する、ということをお聞きし、身近な存在に感じました。
◆トピックコード 113
「時間とは何だろうか【保護者企画】」
お茶の水女子大学 教員 森川雅博 先生
参加生徒数 18名 報告者名 矢口雄翔
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
はじめに、森川先生は「時間について考えてきたこと、主張したいことを、何でも良いから発表してごらん」と仰いました。先生の話を一方的に聴講するのではなく、自分たちで「仮説を立てて議論する」ことが大切だという言葉を聞いて、何人かが口を開き、そして1人の生徒が「時間について調べると、相対性理論の話が出てくるが、よく理解できないので、詳しく教えて欲しい」と、お願いをしたことをきっかけに、森川先生が、理論物理の世界を展開してくださいました。 解説の中には、ベクトル、行列、双曲線関数、極限など、ほとんどの生徒が学習していない数学が出てきましたが、森川先生はその都度、丁寧に説明を挟みながらお話を進めてくださいました。終盤で、テーラー展開された式の第1項と第2項が、よく見知った式になったときには、「おおー!」と感動している声も聞こえました。 また、ネイピア数の説明の過程で、1.01と0.99のそれぞれの365乗の値に大きな差が生じることに例えて、「足るを知る」という、老子の言葉を紹介してくださいました。「持続可能な範囲でいいから、継続して頑張りましょう」という森川先生の言葉は、生徒たちに努力するモチベーションを与えてくださいました。最後に、先生は全員に連絡先を教えてくださり、授業内で紹介してくださった便利なサイトのURLや、今年と昨年の沢山のスライドのデータを共有してくださいました。
順天の生徒や教員のために、手厚い対応をしてくださり、大変ありがたく思います。
2.生徒の感想
・物理に興味がわいた。
・物理や数学をやってみたいと思った。
・複素数が具体的にどのような計算において利用されているかを認識できた。
・双曲線関数を「三角関数の定義を実数だけにしたもの」程度にしか認識していなかったが、宇宙の膨張や特殊相対性理論において双曲線関数が登場し、実際にどのような計算に利用されているかを知れた。
・自然対数の底eを倫理と関連付けた説明をされていて、利息の計算にたとえた説明はよく聞くが、このような説明は初めて聞いたので面白いと感じた。
◆トピックコード 114
「自分を底上げする靴磨きの習慣」
いとの靴磨き屋さん、代表 伊藤 由里絵 先生
参加生徒数 17名 報告者名 齋藤成利
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
生徒が自分の革靴を持参し、伊藤さんが持参してくださった道具で、一人ひとりが自分の革靴を必死で磨いた。この光景は、非常に面白いものであった。冒頭では、伊藤さんの経歴が話され、元警察官であったこと、さらに白バイに乗っていたことに、みんなが驚いた。警察学校で、靴磨きはとても重要視されているようで、そこで得た経験が今に生きているという。現在は「日本中に足元からハッピーを届ける」をモットーに、日本1周靴磨きの旅をしている。靴磨きは、「社会的信用度」を上げる、という言葉を聞いて、はじめは生徒もピンと来ていない様子だったが、伊藤さんのお客さんのお話や、実際に磨かれていく靴の綺麗さや磨かれる前との違いを目の当たりにし、納得した様子へと変わっていった。正しい靴磨きの方法をレクチャーしてもらい、実際に生徒も体験することができ、「全然ちがーう!」「めっちゃ綺麗!」といった、嬉しそうな様子で、靴磨きにのめりこんでいた。た。
2.生徒の感想
・初めて靴磨きをしたが、こんなにも気持ちのいいものだということを感じ、いい経験になった。
・自分で靴を磨いてみて、ビフォーアフターの差に驚いた。こんなにも綺麗になるなら、今までもやっておけばよかったと思った。
・足元から綺麗にすることでしゃきっとするし、今はいている靴も、大事にしていこうと思った。
◆トピックコード 115
「日本が支える世界の開発事業。生き物を守り環境破壊を防ぐ驚きの仕組みとは」
東邦大学 准教授 柴田裕希 先生
参加生徒数 12名 報告者名 土屋有加
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
「経済発展とともに環境に負荷がかかるのは、致し方ないことなのか」この問題から、メインの内容は始まった。「開発 or 環境⇒開発 and 環境」 この考えを実現するための取り組み、「生物多様性オフセット」に賛成か反対か、なぜ反対するのか、議論を行った。生物多様性オフセットは、その土地を開発する代わりに、その場所と同じ価値の生態系を別の場所につくるという取り組みである。多くの生徒は「何もしないよりは良い」と賛成派が多かった。しかし、「別の場所に同じ生態系を作るのは不可能」「その場所の管理をしない企業も出てくる」という、反対意見もあった。
実際、ドイツでは約20年前にその取り組みが行われ、徐々に調査結果が出てきている。結果は、生態系の劣化速度は遅くなっている。つまり、決して悪い取り組みではないことが明らかとなった。このような、今後人類が100年、200年かけて取り組まなければならない環境問題を考えることは、生徒にとっても将来を考える、良いきっかけになったと思われる。
2.生徒の感想
・道路や建物は、すべて日本のお金でできたものではなく、海外からの支援を受けて出来た、というのを知ったこと。日本が先進国となった今、アジアやアフリカを支援しているのは知っていたが、具体的に何を支援しているのかなど、詳しいことは知らなかったため、とても有意義な時間を、講義を通して、過ごすことができてよかった。
・近年、技術の発達に伴い、自然を削って工業などが進んでいる。その際、生き物が死んでしまうが、そこで、他の場所に生き物を増やせば良いという考えは、モラル的に良くないことだと感じた。
◆トピックコード 116
「社会で役立つ発想力の鍛え方」
KIT虎ノ門大学院 教授 三谷 宏治 先生
参加生徒数 12名 報告者名 熊木幸司
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
発想力を鍛えるには、座って考えずに動いてみることが大事、ということが、印象に残る内容のトピックでした。
導入部分で、「知識」があることは大切なことではあるが、ときにその知識は、何かを判断したり、新しいことを試してみたりすることに邪魔になる、ということを、いくつかクイズ形式で、生徒たちに体験を通じて紹介していただきました。また、グループワークでは、紙コップがなぜあのような形をしているのかを、みんな手を動かしながら考えました。重ねて取り出しやすくするための形状であることと、淵の部分が、固くなっていることの必然性を、見出すことができた生徒たちは、いろいろな発想をして実際に手を動かし、行動してみることの重要性が、身を持って体験できたようでした。
2.生徒の感想
・「大人になるにつれて、これまでの知識を使い、考えることをしなくなる、ということを、体験を通して知ることが出来た。
・考えるんだったら動く、ということも、当たり前のようで、実際にはしなくなる。動くとこで、初めてわかることがあり、新しい発見が次々と出てくる。これは、これからの人生で大切な発想力であり、これらを続けることで、また新しい考え方が広がるということをしれました。」
・「講義を通して、事前にある知識が、仇となるような問題は初めてだったので、このようなものもあるのだな、と自分の中で視野が広がった気がした。」
◆トピックコード 117
「世界の開発途上国の現場から: 日本と世界の経済成長と平和のために」
内閣官房 副長官補付内閣参事官補佐 冨田翔 先生
参加生徒数 12名 報告者名 三井田真由美
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
ご自身の現在のお仕事の内容や、JICA時代のイラクやベトナムの経験を踏まえ、日本がなぜ開発途上国の支援に取り組んでいるのか、経済協力、国際社会の問題を幅広くお話いただきました。
2.生徒の感想
・日々のニュースを見たり、目に留まったネット記事を読むだけでは、一生知ることができなかったであろう、政府の仕組みを知ることができたこと。
・「パレスチナ問題」「イラク戦争」「ウクライナ問題」など、よく耳にはするものの、少し敷居が高いように感じてしまい、調べるまでに至らないことを、簡単に要約してくださり、お話ししてくれたことで、思考の幅が広がったように思う。
・途上国には、解決が難しい様々な問題があり、日本が難民を助けるのは、自国のためでもあることを知りました。
・国際支援の重要さを分かった。まだまだ発展途上国が多いことがわかったので、今後、国際経済が、どう移り変わるかが大事だと思う。
・首相の発言に、とてもたくさんの人がかかわっていることがわっかた。
脱炭素政策について、ヨーロッパはプラマイゼロとは言うけれど、アジアはまず、アジアのやりかたで協力するのが良い、とおっしゃった。水素やアンモニアの研究は、日本がかなり進んでいるので、その研究も、ロードマップ制作と同時に、進めていくとのお話をしていただいた。
◆トピックコード 118
「自分らしい生き方」
魔法の質問 プロダクティブディレクター みやじ しげる 先生
参加生徒数 30名 報告者名 橋本実奈
 |
 |
|---|
1. トピック内容等
自分らしい生き方をするためには、どうしたらよいのか。自分の目標が実現できなかった時、なぜできないのだろうではなく、どうしたらできるのか、という考えを持つことの大切さを教えて頂きました。また、自分自身との対話の重要性。一番大切な人は自分であること。
生徒の様子:グループごとの活動。積極的に学年の壁を越えて発言していた。質問の答えはすべて正解、間違いはないと教えて頂いたことを、しっかり理解して互いの意見を尊重していた。
2.生徒の感想
・自分自身の考え方が、大きく変わった。
・できなかったことがあるときは、WHYではなく、HOW、どうしてできなかったのか、考えて行動していきたいと思う。